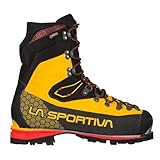松本市の山男です。
今回のブログ記事は、僕が暮らす、信州松本市の温泉のまとめになります。
松本市周辺の、安曇野市(穂高)・大町市エリアの温泉もご紹介します。
わたくし、松本市の山男によるご紹介なので、『この山の登山の帰りには、この温泉』といったこともご紹介します。
長野県には約194の温泉地があり、その数は北海道に次いで全国で第2位です。
長野県の温泉地は歴史のある場合が多く、レトロな雰囲気の温泉宿や、風情のある温泉街が多くあります。
また、自然に溶け込んだ露天風呂も多く、紅葉や雪など、四季折々の景色を眺めながらお湯を楽しめる温泉地も多くあります。
登山口や、スキー場近くにある温泉地もあり、疲れた体を癒すのにぴったりな温泉も多くあります。
今回、ご紹介する松本市、安曇野市、大町市にも、もちろん、歴史あり、自然豊かな温泉が多数あります。
Google map 信州松本市の温泉のまとめ
上のGoogle Mapに、以下でご紹介している温泉のマークをしています。
それでは早速、温泉地のご紹介をしていきます。
浅間温泉(あさまおんせん)
松本の奥座敷と呼ばれる浅間温泉
1300年以上湧き続ける名湯で、長野県内でもトップクラスの湯量を誇ります。
与謝野晶子や竹久夢二など、文人にも愛されてきました。
泉質はアルカリ性単純泉で、浅間温泉の湯は、肌がすべすべになる「美人の湯」とも言われます。
源泉の温度が高いので加温・加水の必要が少なく、浅間温泉は、源泉かけ流しの温泉風呂が多いのも特長です。
浅間温泉には共同浴場もいくつかあり、人々が暮らす温泉地です。
浅間温泉の泉質:アルカリ性単純泉
主な効能:美肌・五十肩・冷え性・腰痛・関節痛・うちみ・くじき・不眠症・抹消循環障害・神経痛など
浅間温泉へのアクセス
松本駅から車で約18分
長野自動車道 松本インターから車で約20分
浅間温泉の近くの山・登山口
美ヶ原(日本百名山)に美須々湖(みすずこ)側からアプローチする際、浅間温泉はほぼ経路上にあります。
登山前日、後日に松本観光をする際の宿として宿泊するのもおすすめです。
浅間温泉で評価の高い宿(2025年現在の旅行サイト)
浅間温泉 四季彩々の隠れ宿 富士乃湯
楽天トラベルなどのリンクです。
長野県松本市浅間温泉3-13-5
[地図]
浅間温泉で日帰り入浴ができる宿
ホテル玉之湯
楽天トラベルなどのリンクです。
長野県松本市浅間温泉1-28-16
[地図]
↑ ↑ ↑
日帰り入浴の可否、時間は宿のホームページなどで最新の情報をご確認ください。
美ヶ原温泉(うつくしがはらおんせん)
1300年以上の歴史がある温泉です。
日本書紀には『束間の温湯』として、美ヶ原温泉(=束の間の温泉)が記されています。
美ヶ原温泉の泉質:弱アルカリ性単純温泉
主な効能:神経痛、動脈硬化症など
美ヶ原温泉へのアクセス
松本駅から車で約21分
長野自動車道 松本インターから車で約23分
美ヶ原温泉の近くの山・登山口
美ヶ原(日本百名山)
山本小屋ふる里館、三城(さんじろ)側から美ヶ原登山をする際、美ヶ原温泉は、松本駅、松本インターとのほぼ、経路上にあります。
美ヶ原温泉で評価の高い宿(2025年現在の旅行サイト)
信州松本 美ヶ原温泉 翔峰
楽天トラベルなどのリンクです。
美ヶ原温泉で日帰り入浴ができる宿
旬彩 月の静香
楽天トラベルなどのリンクです。
長野県松本市里山辺湯の原101
[地図]
↑ ↑ ↑
日帰り入浴の可否、時間は宿のホームページなどで最新の情報をご確認ください。
扉温泉(とびらおんせん)
山の中の閑静な温泉です。
扉温泉は1931年に湯治場として開湯しました。
扉温泉の「扉」は、古くから伝わる天照大神の岩戸伝説に由来すると言われています。
扉温泉の泉質:アルカリ性単純泉
主な効能:美肌・五十肩・冷え性・腰痛・関節痛・うちみ・くじき・不眠症・抹消循環障害・神経痛など
扉温泉へのアクセス
松本駅から車で約35分
長野自動車道 松本インターから車で約40分
扉温泉の近くの山・登山口
美ヶ原(日本百名山)
山本小屋ふる里館、三城側から美ヶ原登山をする際、扉温泉は、松本駅、松本インターとのほぼ、経路上にあります。
扉温泉で評価の高い宿(2025年現在の旅行サイト)
扉温泉 明神館
楽天トラベルなどのリンクです。
白骨温泉(しらほねおんせん)
標高約1400mにある山岳温泉です。
『3日入れば、3年風邪をひかない』とも伝わる白骨温泉。
絹のような肌触りと言われる湯で、子供の肌にもやさしい弱酸性です。
歌人の若山牧水が、湯治場として何度か白骨温泉に足を運んでいます。
『白骨の温泉は、空気に触れて白くなる』と言われますが、温泉が空気に触れることで反応する等の要因です。
飲むことができる温泉で、飲泉所が2か所に設置されています。
白骨温泉の泉質:単純硫化水素泉
主な効能:胃腸病・婦人病・肝臓病・神経症・呼吸疾患・慢性疲労・美肌に効果
白骨温泉へのアクセス
松本駅から車で約1時間8分
長野自動車道 松本インターから車で約1時間5分
白骨温泉の近くの山・登山口
乗鞍岳の休暇村乗鞍高原、三本滝側からの登山前後に。
白骨温泉は、新穂高(岐阜県)、上高地、焼岳(中の湯登山口)から松本駅、松本インターに向かう際のほぼ経路上にあります。
新穂高は、槍ヶ岳、穂高岳、笠ヶ岳、鷲羽岳、水晶岳などの登山の起点です。(上高地からは別ルート)
上高地は槍ヶ岳、穂高岳などの登山の起点です。(新穂高とは別ルート)
上記の山々はすべて日本百名山です。
白骨温泉で評価の高い宿(2025年現在の旅行サイト)
白骨温泉 白船荘新宅旅館
楽天トラベルなどのリンクです。
白骨温泉で日帰り入浴ができる宿
泡の湯旅館
楽天トラベルなどのリンクです。
↑ ↑ ↑
日帰り入浴の可否、時間は宿のホームページなどで最新の情報をご確認ください。
のりくら温泉郷
乗鞍岳のある乗鞍高原にある、のりくら温泉郷。
のりくら温泉郷には、以下の3つの異なる源泉があり、乗鞍三湯と呼ばれています。
泉質と効能が異なる温泉を楽しむことができます。
・乗鞍高原温泉
・すずらん温泉
・安曇乗鞍温泉
それぞれの温泉についてご紹介です。
乗鞍高原温泉
乗鞍岳の中腹からわき出る温泉を乗鞍高原に引湯している温泉です。
乳白色の単純硫黄泉で、独特なにおいがあります。
殺菌力が強く、体を芯からあたため、新陳代謝が活発になると言われています。
乗鞍高原温泉の泉質:単純硫黄泉(硫化水素型/弱酸性低張性高温泉)
主な効能:筋肉疲労、冷え性、アトピー(慢性皮膚病)、慢性婦人病、切り傷、糖尿病、高血圧症などの改善が期待
乗鞍高原温泉へのアクセス
松本駅から車で約1時間5分
長野自動車道 松本インターから車で約56分
乗鞍高原温泉の近くの山・登山口
長野県側からの乗鞍岳登山(日本百名山)
乗鞍高原温泉で評価の高い宿(2025年現在の旅行サイト)
信州乗鞍高原温泉 御宿 こだま
楽天トラベルなどのリンクです。
乗鞍高原温泉で日帰り入浴ができる宿
乗鞍高原温泉 あったか温泉宿 美鈴荘
楽天トラベルなどのリンクです。
長野県松本市安曇乗鞍高原温泉4085-49
[地図]
↑ ↑ ↑
日帰り入浴の可否、時間は宿のホームページなどで最新の情報をご確認ください。
すずらん温泉
乗鞍高原内にわき出ている、無色透明で刺激の少ない温泉です。
単純温泉(低張性中性温泉)のため、刺激が少なく、赤ちゃんや、肌の弱い方にも優しい温泉です。
すずらん温泉の泉質:単純温泉(低張性中性温泉)
主な効能:筋肉疲労、冷え性、自律神経不安定症、不眠症、うつ状態などの改善が期待。
すずらん温泉へのアクセス
松本駅から車で約1時間5分
長野自動車道 松本インターから車で約55分
すずらん温泉の近くの山・登山口
長野県側からの乗鞍岳登山(日本百名山)
すずらん温泉で評価の高い宿(2025年現在の旅行サイト)
乗鞍高原の宿 irodori
楽天トラベルなどのリンクです。
長野県松本市安曇4085-36
[地図]
安曇乗鞍温泉
地下1300mからわき出るカルシウムやマグネシウムを多く含む温泉です。
カルシウム、マグネシウムを多く含む無色透明の炭酸水素塩泉です。
ほんのり金気臭(かなけしゅう)がします。
※鉄分を多く含む温泉特有の鉄サビのような匂いです。
サラサラのお湯は、美人の湯ともいわれています
安曇乗鞍温泉の泉質:カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉(低張性中性低温泉)
主な効能:筋肉疲労、冷え性、やけど、慢性皮膚病の改善が期待。
安曇乗鞍温泉へのアクセス
松本駅から車で約1時間11分
長野自動車道 松本インターから車で約1時間2分
安曇乗鞍温泉の近くの山・登山口
長野県側からの乗鞍岳登山(日本百名山)
安曇乗鞍温泉で評価の高い宿(2025年現在の旅行サイト)
乗鞍高原温泉 休暇村 乗鞍高原
楽天トラベルなどのリンクです。
安曇乗鞍温泉で日帰り入浴ができる宿
上記の『休暇村 乗鞍高原』で日帰り入浴ができます。
↑ ↑ ↑
日帰り入浴の可否、時間は宿のホームページなどで最新の情報をご確認ください。
中の湯温泉(なかのゆおんせん)
1915年(大正4年)に創業の温泉。
山あいの湯で、身も心も大自然に溶け込む温泉です。
源泉かけ流しで、柔らかい湯です。
中の湯温泉の泉質:単純硫黄泉
主な効能:疲労回復・冷え性・腰痛・糖尿・神経痛・健康回復
中の湯温泉へのアクセス
松本駅から車で約1時間8分
長野自動車道 松本インターから車で約1時間
中の湯温泉の近くの山・登山口
焼岳(日本百名山)。
中の湯温泉は、新穂高から松本インター、松本駅へ向かう際のほぼ経路上にあります。
中の湯温泉で評価の高い宿(2025年現在の旅行サイト)
中の湯温泉旅館
楽天トラベルなどのリンクです。
中の湯温泉で日帰り入浴ができる宿
上記の『中の湯温泉旅館』で日帰り入浴ができます。
↑ ↑ ↑
日帰り入浴の可否、時間は宿のホームページなどで最新の情報をご確認ください。
沢渡温泉(さわんどおんせん)
日本でも屈指の観光地の上高地の玄関口にある温泉です。
上高地まではバス、タクシーで約30分の距離です。
※マイカー規制のため、上高地にはマイカーで行くことはできません。
白骨温泉、乗鞍高原への公共交通の基地にもなっています。
沢渡温泉の湯は、前述の中の湯温泉から引湯されています。
沢渡温泉の泉質:単純硫黄泉
主な効能:疲労回復・冷え性・腰痛・糖尿・神経痛・健康回復
沢渡温泉へのアクセス
松本駅から車で約59分
長野自動車道 松本インターから車で約49分
沢渡温泉の近くの山・登山口
沢渡温泉は、上高地(槍ヶ岳、穂高岳などの登山口)に行く際にマイカーを駐車する沢渡の駐車場の最寄りの温泉です。
新穂高、焼岳(中の湯温泉)から松本駅、松本インターに向かう際の経路上にあります。
沢渡温泉で評価の高い宿(2025年現在の旅行サイト)
さわんど温泉 上高地ホテル
楽天トラベルなどのリンクです。
長野県松本市安曇さわんど温泉4171
[地図]
さわんど温泉で日帰り入浴ができる宿
上記の『さわんど温泉 上高地ホテル』で日帰り入浴ができます。
↑ ↑ ↑
日帰り入浴の可否、時間は宿のホームページなどで最新の情報をご確認ください。
上高地温泉(かみこうちおんせん)
標高1500メートルの上高地に、文政年間(1830年代)から、湧き続ける温泉です。(以下でご紹介の温泉宿の湯)
上高地温泉の泉質:単純温泉(弱アルカリ性低張性高温泉)
主な効能:胃腸病、皮膚病、疲労回復
上高地温泉へのアクセス(さわんどバスターミナル)
松本駅から車で約1時間4分
長野自動車道 松本インターから車で約52分
※上高地にはマイカーで行くことはできません。マイカーの場合、さわんどに車を駐車(有料)し、バスまたはタクシー(約30分)で上高地まで行くこととなります。
上高地温泉の近くの山・登山口
上高地は、穂高岳、槍ヶ岳、焼岳や、日本屈指の紅葉スポット・テント村で有名な涸沢(からさわ)への登山の起点です。
上高地温泉で評価の高い宿(2025年現在の旅行サイト)
上高地温泉ホテル
楽天トラベルなどのリンクです。
長野県松本市安曇上高地4469-1
[地図]
上高地温泉で日帰り入浴ができる宿
上記の『上高地温泉ホテル』が日帰り入浴可です。
↑ ↑ ↑
日帰り入浴の可否、時間は宿のホームページなどで最新の情報をご確認ください。
崖の湯温泉
『崖の湯』の名は、鎌倉時代に起きた崖崩れの断層から温泉が湧いたことに由来していると言われています。
猿が崖の湯温泉の湯で傷を癒している様子が発見され、以来、湯治場として人々に親しまれてきたと言われています。
崖の湯温泉からは、松本平(松本盆地)を見下ろすことができ、その向こうに北アルプスを眺めることができます。
崖の湯温泉の泉質:カルシウム・マグネシウム-硫酸塩・炭酸水素塩冷鉱泉(中性低張性冷鉱泉)
主な効能:神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節のこわばり・うちみ・くじき・慢性消化器病 ・痔疾・冷え性・病後回復期・疲労回復・健康増進・きりきず・やけど・慢性皮膚病など
崖の湯温泉へのアクセス
松本駅から車で約29分
長野自動車道 松本インターから車で約23分
崖の湯温泉の近くの山・登山口
崖の湯温泉は、鉢伏山と高ボッチ高原の山腹にあります。
高ボッチは富士山の撮影スポットとして知られます。
高ボッチ、鉢伏山ともに、北アルプスの山々を眺めることができます。
鉢伏山、高ボッチは、車で行くことができます。(冬季通行止めありです。災害により通行不可の場合あり。)
崖の湯温泉の宿
薬師平 茜宿(薬師平ホテル)
楽天トラベルなどのリンクです。
大町温泉郷(おおまちおんせんきょう)
大町温泉郷は、立山黒部アルペンルートの玄関口(長野県側)にある温泉郷です。
立山黒部アルペンルートは、北アルプスを貫く全長37.2kmルートで、世界でも有数の山岳観光ルートです。
また、黒部ダム観光の玄関口でもあります。
大町温泉郷は、アルペンルート(黒部ダム観光)の玄関口となる扇沢駅まで車で約15分の場所に位置します。
大町温泉郷の湯は、次にご紹介の葛温泉(くずおんせん)から引湯されています。
大町温泉郷の泉質:単純温泉(弱アルカリ性低張性高温泉)
主な効能:神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進など
大町温泉郷へのアクセス
信濃大町駅から車で約15分
松本駅から車で約57分
長野自動車道 松本インターから車で約46分
大町温泉郷の近くの山・登山口
爺ヶ岳(日本三百名山)や鹿島槍ヶ岳(日本百名山)の柏原新道登山口と、針ノ木岳(日本二百名山)の扇沢登山口。
断崖絶壁で難易度が高いルートとして知られる下ノ廊下を黒部ダム側からスタートする場合。
大町温泉郷で評価の高い宿(2025年現在の旅行サイト)
大町温泉郷 信濃の里 ときしらずの宿 織花
楽天トラベルなどのリンクです。
大町温泉郷で日帰り入浴ができる宿
大町温泉郷 黒部観光ホテル(BBHホテルグループ)
楽天トラベルなどのリンクです。
↑ ↑ ↑
日帰り入浴の可否、時間は宿のホームページなどで最新の情報をご確認ください。
葛温泉(くずおんせん)
高瀬渓谷に佇む、秘湯「葛温泉」
 
大町市の温泉です。
 
葛温泉は湯量が豊富で、大町温泉郷の湯は、主に葛温泉から引湯されています。
 
葛温泉は、北アルプスへの登山ルート「裏銀座縦走路」の登山口近くに位置し、古くから登山者に親しまれてきた温泉です。
ほのかな硫黄の香りがする湯です。
葛温泉の泉質:単純温泉
主な効能:自律神経不安定症、不眠症、うつ状態、筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下、軽症高血圧、耐糖能異常、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状、病後回復期、疲労回復、健康増進
葛温泉へのアクセス
大町駅から車で約22分
松本駅から車で約1時間7分
長野自動車道 松本インターから車で約1時間13分
葛温泉の近くの山・登山口
北アルプス裏銀座の登山口となる七倉まで、約10分の場所に位置する葛温泉
七倉は、烏帽子岳(日本二百名山)、野口五郎岳(日本三百名山)、船窪岳の登山口になります。
葛温泉で評価の高い宿(2025年現在の旅行サイト)
秘湯 葛温泉 温宿かじか
楽天トラベルなどのリンクです。
葛温泉で日帰り入浴ができる宿
葛温泉 高瀬館
楽天トラベルなどのリンクです。
長野県大町市平高瀬入2118-13
[地図]
↑ ↑ ↑
日帰り入浴の可否、時間は宿のホームページなどで最新の情報をご確認ください。
まとめ
以上、『松本市の温泉まとめ』でした。
北アルプスをはじめとした登山者憧れの山々がある松本市。
そして、松本市には歴史のある温泉もたくさんあります。
登山と温泉はワンセットと言っても過言ではありません。
名だたる山々と、温泉をセットにすることができる松本市。
今回の記事が、登山好き、温泉付きの方々のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
それではまた、次の山トークでお会いしましょう!
『僕の行きつけの温泉・日帰り入浴施設』を、こちらでご紹介しています。
『松本駅周辺の観光&グルメスポット』を、こちらでご紹介しています。
『松本市から眺めることができる山々』を、こちらでご紹介しています。
レンタカー予約の『Jcation』
大手レンタカー会社を一括で比較して、予約をすることができます。