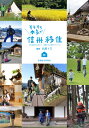松本市の山男です。
岳都松本に暮らす松本市民は、山を知らず、登山者率も低いです。
今回は、『どうやったら松本市民に山を知ってもらえるか』を含め、松本市民の僕が山トークをしていきます。
僕の体感として、松本平から眺めることができる山々を、山を指さして、山名を5つ以上答えられる松本市民は5人に1人いないと思います。
常念岳、乗鞍岳、美ヶ原、鹿島槍ヶ岳、五竜岳などなど。
僕の職場に限って言えば、10人に1人いるかいないかだと思います。
全国の登山者が憧れる北アルプスの山々。
松本市民は、そんな名だたる山々を見上げて日常生活を送っているのに、山を知らないというのは勿体なすぎると僕は思っています。
※僕の登山ブログをお読みいただく上でのご注意 → こちらからお読みください。
岳都に暮らす松本市民は山を知らず登山者率も低い
山が身近すぎる
夜空を見上げれば星がありますが、星座や星の名前を知っている人はあまりいないかと思います。
松本市民にとっての山は、多くの人にとっての星と同じような存在です。
そこにあって当たり前のもの。
生まれた時からすぐそこにある身近なものです。
近くにありすぎるからこそ、その存在について、深く追求しないのかもしれません。
岳都に暮らす松本市民は山を知らず登山者率も低い②
教えてくれる人がいない
松本市民で、詳しく山を知っている人は、5人に1人?僕の職場では10人に1人?というお話しをさせてもらいました。
つまり、自分の周りにいる松本市民は、ほとんどの人が、山を詳しく知らないということになります。
自分の周りに山名を教えてくれる人はほとんどいない状況ということになります。
家族を含めて。
岳都に暮らす松本市民は山を知らず登山者率も低い③
松本市民は登山をしない
体感として、アラフォーの僕が接することがある松本市民の登山者率は5%に行くか行かないかです。
数十人の松本市民がいた場合、登山が趣味の人は感覚的には数名です。
どんな人付き合いがあるか、どんな職場にいるか、世代によってもバラツキがあるかと思いますが、僕の知人、同僚で登山をしている松本市民は数人です。
岳都に暮らす松本市民は山を知らず登山者率も低い④
今日は山が綺麗だ
山を知らない松本市民ですが、山を見てはいます。
天気が良い日には、『今日は山が綺麗だね〜』という声が聞こえてくることもあります。
ただ、今日は『鹿島槍ヶ岳がきれいだね』とか、『美ヶ原が雪で白くなったね。』など、具体的な山名があげられている会話はほとんど聞いたことがありません。
※鹿島槍ヶ岳は松本市にある山ではありませんが、松本市から眺めることができます。
岳都に暮らす松本市民は山を知らず登山者率も低い⑤
松本市民に山を知ってもらうには
学校で教えるというのが最も効果的かと思います。
※学校現場が多忙を極めているということは、ニュースなどにより知っているつもりです。そいったことは度外視して、好き勝手に書いている記事ですので悪しからず。
※今は、学校現場で教えられているのかもしれません。
学校で山を教える方法としては、『山名クイズ』のようにして、例えば、その学校から見える山の写真を撮って、記述の枠を設けて、山の名前を答えさせる、という方法があるかと思います。
山名だけでなく、その山の標高をクイズの内容に加えたり、その山が日本百名山か否かもクイズにするというのもありだと思います。
ちなみに僕は、とある人から依頼を受けて、とある会社の社員食堂から見える山を写真撮影し、データ加工して山の名前を記したものを作成しました。
その写真データは印刷されて、社員食堂の窓に貼られました。
印刷された写真データを見れば、社員食堂から見えている山が、なんという名前の山なのかがすぐにわかります。
同じようなものの『学校から見える山』バージョンを学校現場で取り入れて、クイズのような形で扱えば、松本市民は子供のうちから山に関心を持つようになると思います。
北アルプスという、松本市ならではの最高の教材が、現状、学校現場で全く生かされていないというのは本当にもったいないことだと思います。
松本市では、学校登山が行われている学校もありますが・・・
学校登山についてはこちらでブログ投稿をしています。
『学校登山で登山が嫌いになる【長野県民あるある】』
岳都に暮らす松本市民は山を知らず登山者率も低い⑥
山を知ることは良いことなのか
北アルプスという松本市ならではの最高の教材。
学校現場で生かされていないのはもったいないと思う一方で、思うこともあります。
例えば、自分が学校の教員で、自分のクラスの生徒に山を教え、その結果自分の教え子が登山をするようになったとします。
そして、万が一、その生徒が山で遭難をした場合、僕は生徒に山を教えたことを悔やむかもしれません。
登山は無慈悲な自然の中でするものであるということを考えると、子供たちに山を教えるということは一概に良しとすることはできないのかもしれません。
学校や家から見える山名を知り、眺めているくらいがちょうど良いのかもしれません。
まとめ
以上、『岳都に暮らす松本市民は山を知らず登山者率も低い』ということで、山トークをしてきました。
①松本市民には山が身近すぎる
②教えてくれる人がいない
③今日は山が綺麗だ
④松本市民に山を知ってもらうには
⑤山を知ることは良いことなのか
松本市民は生活の中に山があります。
「松本市民の登山者率を上げよう!」というのは極端な話しかもしれません。
自然を相手にすることになる登山は危険を伴いますし、普及活動をすれば遭難事故件数が増えてしまうかもしれません。
ただ、松本市民なのに、目の前にある山、生活の中にある山の名前は知らないというのは少し寂しいように思います。
県外からの親戚や友達を松本に迎えたときに、山を教えることができるということは、松本の魅力を教えるということになると思います。
僕は自分の子供には、家から見える山々をしっかりと教えていきたいと思ってます。
僕のように山にのめり込んで欲しくはありませんがw
あの山の名前を知りたい
山並み大図鑑 信州山座同定navi
松本市について、松本市民の僕が書いたブログ記事をこちらで一覧にしています。
『夏山登山のノウハウ』を、こちらでブログ投稿しています。日本百名山の完登、毎週末の北アルプス登山で身に着けた、冬山登山にも通じるノウハウになります。
『僕の夏山登山装備(登山ウェア含む)』は、こちらで一覧で紹介しています。お問い合わせいただくことが多いので。