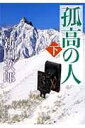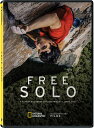『山は逃げない』と言いますが、僕は『山は逃げる』と思っています。
『山は逃げない』
映画なのか、ドラマなのか、気がついたら『山は逃げない』というフレーズが僕の頭に刷り込まれています。
多分、登山をするようになる前から。
『山は逃げない』と言われるシーン
『山は逃げない』が言われるシーンとしては、以下のようなシーンが思い浮かびます。
・荒天の中、山頂アタックを諦めて撤退をする。
・エベレストなどのベースキャンプで、山頂アタックの機会をうかがうも、天候によりアタックを諦めて帰国の途につく。
『山は逃げない』を具体的に言うと
『山は逃げない』という言葉の裏には、以下のような意味があるのかなと思います。
『せっかくここまで登ったのに、諸事情(荒天など)により山頂まで行けなそうだ。まあ、山は逃げないんだから、今回は潔く諦めて下山しよう。』
『今回は諸事情により撤退したけど、撤退は正しい判断だった。山は逃げないんだから』
確かに、見かけじょうは『山は逃げない』
見かけ上は、山は逃げません。
その場に行けば、いつだって山はそこにあります。
人間の寿命からすれば、山は未来永劫、その場にあり続けます。
つまり、物理的には山は逃げないということです。
実際には『山は逃げる』
物理的には、『山は逃げない』ですが、状況としては『山は逃げます』
『山は逃げる』を厳密に言うと、山に登る機会(チャンス)と、そのときの自分のコンディションが逃げていくということになります。
山に登る機会は逃げる
例えば、長野県松本市に住む僕が、北海道の山に登るというのは、なかなか気軽にできることではありません。
北海道登山で、荒天のため撤退したとしたら、もう二度と北海道登山をすることはないかもしれません。
また、近頃、僕もパパになりましたが、パパになった今、山に登る機会を得るのは、一段と難しくなりました。
独り身だったころは、登山に明け暮れることができていましたが、結婚して子供が生まれ、育児をしている今、そう簡単に長丁場の山に登ることはできません。
ましてや、遠征登山となると・・・。
そう、山に登る機会は逃げます。
自分のコンディションは逃げる
人間、誰しも歳をとります。
運動能力と体力は低下していきます。
また、常に登山をするためのコンディションを維持できるわけではありません。
僕は、独り身だったころは、ランニングなどでしっかりトレーニングをしたうえで、登山をしていました。
つまり、山仕様の体で登山をすることができていました。
しかし、今は独り身だったころと比べ、十分なトレーニングができていません。
まったくもって、山仕様の体ではなくなってしまいました。
山は逃げないかもしれませんが、『自分のコンディションは逃げる』です。
また、同じ山に登るとしても、山仕様の体だったときと、山仕様でない体になった時とでは、全く違う登山になります。
登山スピードが変われば、見える景色、景色の感じ方も変わります。
山仕様の体だったときは登頂できた山も、山仕様でない体になってしまっては登頂できないということもあります。
そう、『自分のコンディションは逃げる』=『その時の山は逃げる』ということです。
まとめ
以上、『山は逃げないというけれど、山は逃げます』ということで、山トークをしてきました。
①『山は逃げない』と言われるシーン
②『山は逃げない』を具体的に言うと
③確かに、見かけじょうは『山は逃げない』
④実際には『山は逃げる』
⑤山に登る機会は逃げる
⑥自分のコンディションは逃げる
山は逃げないと言いますが、山は逃げます。
確かに、物理的には山は逃げませんが、山に登る機会、山に登る自分のコンディションは逃げます。
正確に言えば、山は逃げるというよりは、自分が、山に引き離されていくと言った方が良いのかもしれません。
でも、仮に、山に引き離されたとしても、自分次第で追いかけることができます。
逃げる山を追いかけ続けるのが、真の山好きなのかなと思います。
ちなみに僕は、無職になって日本百名山登山に明け暮れたことがあります。
短期間で日本百名山を完登するという挑戦登山でした。
146日間という短期間で日本百名山を完登することができましたが、結婚をして赤ちゃんが生まれた今では絶対にできない挑戦です。
当時、日本百名山登山という、大きな大きな山を、逃がさずに登ることができたと思っています。
日本百名山登山については、以下でブログ投稿をしています。
無職(ニート)となって挑んだ日本百名山登山を振り返って思うこと【一生に一度きりの登山】
『山は逃げないというけれど、山は逃げる。』
これからも、できる限り、山を追いかけていきたいと思います。
妻と子供に逃げられない程度に 笑
それではまた、次の山トークでお会いしましょう!!
山にも通じる?
ドラマ 逃げるは恥だが役に立つ
『日帰り登山のノウハウ』をこちらでブログ投稿しています。日本百名山の完登、毎週末の北アルプス登山で身に着けたノウハウになります。
『僕の登山装備(登山ウェア含む)』をこちらで一覧で紹介しています。お問い合わせいただくことが多いので。